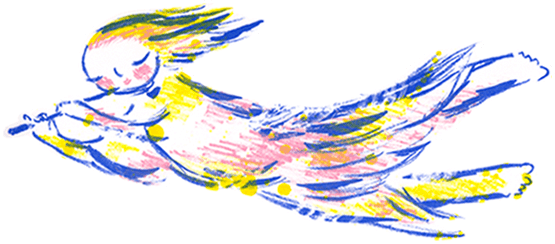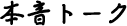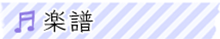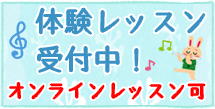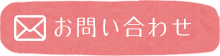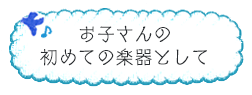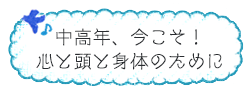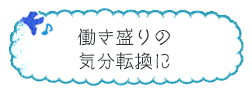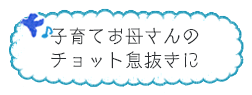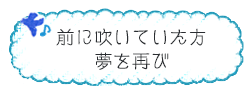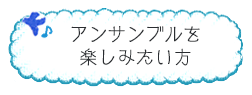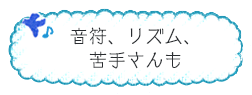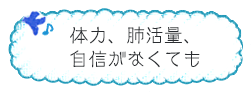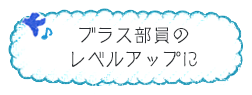音楽の受け止め方千差万別
奥原由子
同じ曲でも人それぞれ受け止め方はかなり違いますよね。
純粋にメロディや響きを味わって楽しむ。
音の組み立てや構造に惹かれる。
作者の生きた時代背景や生涯なども知りたくなる。
性格、生き方、考え方、社会との関係などなど詳しく知りたい。等々。
同じ人でも同じ音楽が年齢や状況によって感じるものが変わってくる。
子供の時は訳など考えないけど夢中になる。
大人になってあの気持ちは何だったんだろう、と客観的に思い返したりする。
今ならもっと深く受け止められる、などと思ったりもする。
そんな体験あるでしょ。
そして名曲ほど、多くの人の共感を呼ぶ一方、それぞれの心に呼び醒ますものが多面的である様に思います。
音楽と文学の違いはありますが、作品と受け手の摩訶不思議な交感を、先月取り上げたル・グウィンの「空飛び猫」シリーズのあとがきで、村上春樹さんが素敵に表現しています。
内容を要約させていただいてご紹介します。
もちろん、ぜひ実際にご本人の書かれたものを読むことをお勧めしつつです。
▶︎ 人それぞれの受け止め方や入り込み方の違い。
ファンタジーというものはとても個人的で、ある人にはうまく「はたらく」けど別の人にはぜんぜん「はたらかない」。一度強く「はたらいてしまった」ら、あなた個人に向かって開いた窓になり、その世界の空気を吸い込み、その世界の光を実際に見ることになる。
▶︎ 年齢的な受け止め方の違い。
あなたは今、20歳かもしれないし60歳かもしれない。ファンタジーを読むのに年齢制限はありません。でも、できることなら、もっと大きく空気を吸い込めて、もっとたくさんの光を見ることができる10歳のころに戻って読んでみたいなという気持ちを抱かれるかもしれませんね。
(子供の頃の柔軟な感性を忘れないで、ということ?)
▶︎ 何にスポットを当てて味わうか。
ストーリーや雰囲気、登場人物のキャラクターなどを味わうのも良し。
でも、作者が作品に込めた意図、寓意も頭の隅にとめておいていただきたい。
以上、さすが的確ですね。
私に「はたらいた」音楽は、本当に村上さんの言うとおり、心の窓を開けて爽やかな空気と明るい光でゆくてを示してくれるように思います。
あなたに「はたらいた」のは、どんな音楽ですか。